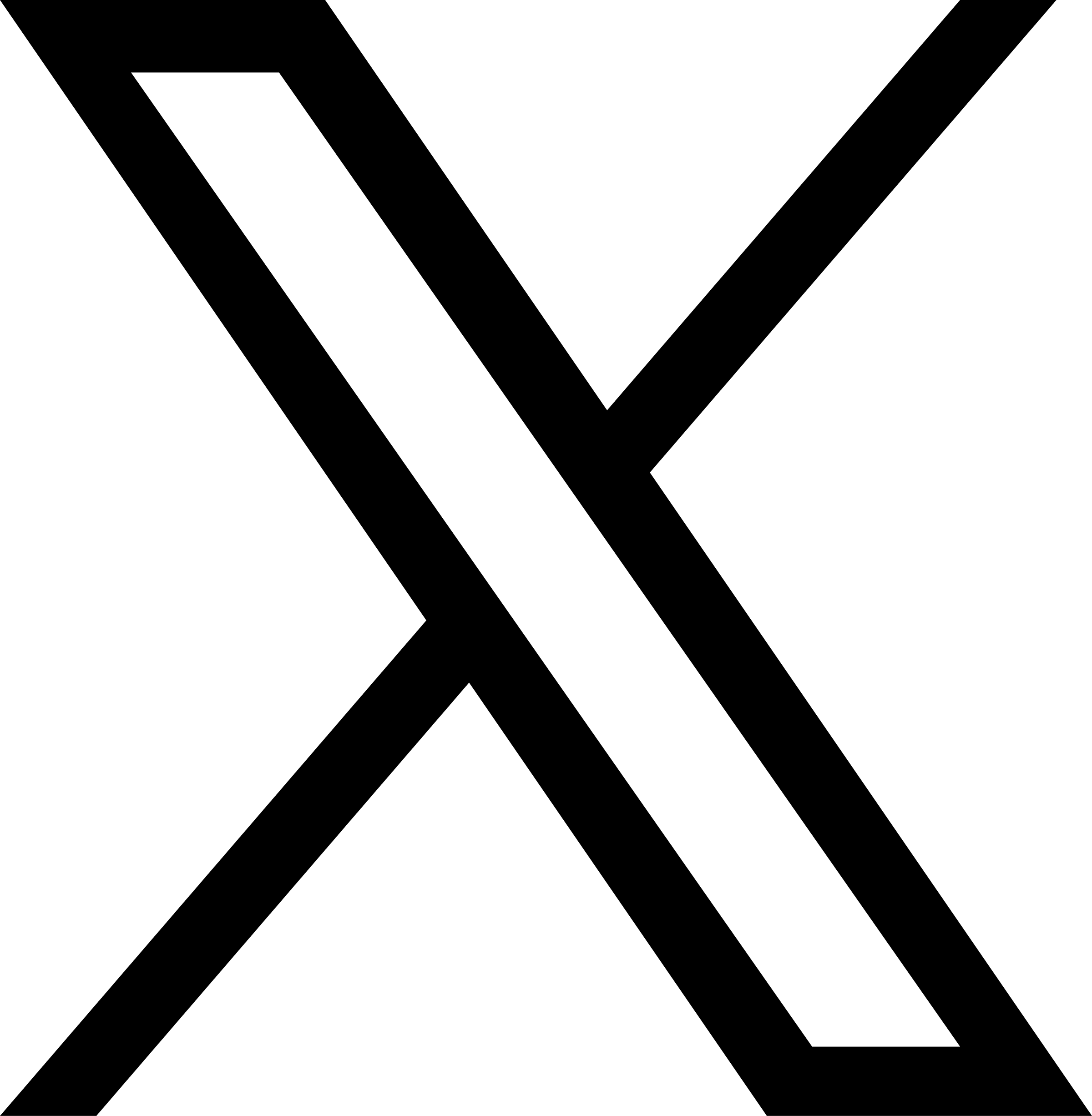マンション管理
マンション管理相談
管理規約の変更について
- いまある管理規約では実情に合わないことが発生しているので、管理規約の一部変更について、教えてください。
法令に違反しない内容であれば、管理規約を変更することは可能です。
マンションの管理と使用についてはマンション管理規約で定めており、変更案は理事会が作成し、総会で決議します。規約を変更することで、一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼす場合、その区分所有者の承諾が必要です。また、賃借人の利害に関する変更の場合は、賃借人は、総会に出席して意見を述べることができます。
バルコニーの使用について
- バルコニーに物置を置いている居住者に対して注意したほうがよいか、教えてください。
バルコニーは共用部分であり、安全性や美観の点から、管理規約や使用細則に基づいて、物置の撤去を求める必要があります。火災等が発生した場合に避難路を塞ぐことになり大変危険です。また、バルコニーに物を置くと雨水の排水を妨げることになります。管理組合名で、口頭や文書等による注意が必要です。
漏水事故の対処について
- 漏水事故が発生した場合の対処の方法について、教えてください。
漏水事故の主な原因は、入居者の不注意等により起こる場合と経年劣化で起こる場合があります。 居住者の不注意等で起こるケースとして、洗濯機の給水・排水ホースが外れたため、階下へ水が漏れたり、トイレに異物を流した場合やバルコニーの排水口の詰まり等が考えられます。 経年劣化による原因としては、給排水管の接続部分の緩みやパッキンの老朽化、屋上防水の劣化、外壁目地(シーリング材)の劣化、外壁のモルタル・タイル等のひび割れ等が考えられます。 共用部分については、管理組合として定期点検や計画的な修繕を行ない、専有部分に関しては、各居住者で注意する必要があり、共用部分は管理組合で、専有部分は入居者で損害保険を付保すると良いでしょう。
管理組合費等の滞納
- 管理組合費等を滞納している人に対しての督促方法について、教えてください。
未納の組合員の第一次督促として、電話又は文書による督促をし、第二次督促として、訪問又は督促状の送付、第三次督促として、管理組合の名義で内容証明等による督促を行います。その後、裁判所への支払督促の申し立てや弁護士等への相談・依頼を行います。
地震対策について
- マンションの地震対策について、教えてください。
地震への備えとして、普段より建物の内外をチェックし、危険箇所を発見し、早めに補修することが大切です。 管理組合が備えて置くものとして、工具類やスコップ・バール等が考えられますが、いざという時にすぐ役立つよう、チェックして置くことが必要です。 組合員・居住者の名簿、緊急時の連絡先名簿の把握や避難の方法、避難場所の確保なども決めておく必要があります。
管理会社の変更について
- 現在の管理会社に不満なので、管理会社の変更について教えて下さい。
管理費用の多寡やサービス内容の面で折り合わない場合、管理会社を変更するのも選択肢の一つです。管理会社との契約を解除するには契約書の解除の項目を確認しつつ、管理費の安さだけにとらわれず、委託する業務内容や入居者のニーズも考えてメリットとデメリットを十分に考慮したうえで行うことが大切です。
住人の騒音問題
- 近隣の部屋からの騒音問題の対応について教えて下さい。
隣家の楽器演奏や階上の足音など生活騒音のトラブルはマンションで起こり易く深刻化しやすいものです。当事者同士で解決できない場合、理事を交えて両者の話を聞き妥協点を提案します。騒音の大きさや時間が常識外であれば、区分所有法の有害行為や共同の利益に反する行為になるので騒音測定器での客観的データを示して改善を提案する方法もあります。
管理組合総会について
- 総会に出席する人が少ないので増やす為の方法を教えて下さい。
管理組合としては、組合員が管理組合運営に関心を持ち総会での多くの組合員の出席で活発な意見交換が行なわれ、また白紙委任ではなく議決権行使が行なわれるよう工夫が必要です。例えば、多くの組合員が出席できるような適当な場所・時間の設定、開催日時の早期の決定、理事会議事録の配布・広報誌の発行等住民と管理組合との意思疎通を深める機会を工夫することなどがあります。
大規模修繕工事の専門家への依頼
- 大規模修繕工事を外部の専門家に依頼するのに、どのように依頼すれば良いですか、教えて下さい。
工事の依頼は、施工者とは別の専門家に修繕設計・工事監督等を依頼する「設計監理方式」と、修繕設計・工事の施工・監理を同じ組織に依頼する「責任施工方式」があります。設計監理方式は施工者とは独立した第三者による工事内容のチェックが期待でき、責任施工方式は1つの組織に工事全体を依頼できるので管理組合の労力は少なくて済みます。それぞれ一長一短があり、実情に合わせて選択して下さい。
組合員名簿等の個人情報の取扱いについて
- 組合員名簿等の個人情報の取扱いにどのような対応が必要ですか。教えて下さい。
平成29年5月に個人情報保護法が改正され、これまでマンション管理組合には適用されなかったところ、個人情報の数の枠が撤廃され5千件以下でも適用されることになりました。組合員名簿は管理費徴収、総会招集通知の送付、災害時の安否確認時などに必要なため作成、保管、閲覧等が標準管理規約で義務付けられています。データの漏洩、滅失、毀損の防止や安全管理に必要な措置を講じなければなりません。
分譲マンション管理組合について
- 中古の分譲マンションを購入することになりました。管理組合があると聞いたのですが、どういう団体ですか?また、加入しなくてもよいですか。
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その部分の所有権を「区分所有権」といい、この区分所有権を有する者を「区分所有者」といいます。
そして、区分所有者が複数となったときに、すべての区分所有者が参加して、建物やその付属施設などを維持・管理していくための団体を設立することになります。
この団体のことを、マンション管理適正化法では「管理組合」といいます。なお、区分所有者にとっては管理組合へ加入することが義務ですし、また、脱退することはできません。
分譲マンション管理組合について
- 区分所有者から、マンション管理組合の修繕積立金を返してほしいので、マンションの管理組合を解散してはどうか、と尋ねられました。解散することはできますか?
区分所有法には、管理組合法人の解散に関する規定はありますが、管理組合の解散については規定されていません。まず、管理の対象となる建物が建替えなどで取り壊すことにより滅失する場合は、管理組合が当然解散することになるでしょう。しかし、建物が存在する場合は、これを管理することは区分所有者全員の義務ですから、仮に管理組合の解散を総会で議決したとしても、管理する団体を何らかの形で設けなければならない、ということです。
管理組合として形式上あるいは名目上の解散はできるかもしれませんが、実質的には、建物管理するための団体を区分所有者全員によって別に構成・設立しなければなりません。
区分所有法第三条は「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と規定しています。「管理を行うための団体を構成し、・・できる。」とあるのは「団体を構成することができる」と読むのではなく、「区分所有者は、全員で、・・・管理を行うための団体を構成し、」でいったん文脈は切れる、つまり「必ず団体を構成しなければならない」と解するものとされています。
その意味では、強行規定ともいえますので、管理組合の解散を集会で議決したとしても、この議決は無効であり、管理組合を解散することはできない、ということになります。以上、任意団体である自治会や町内会あるいは同窓会や親睦会への加入は任意であって、また自由に解散することができることと異なり、管理組合については区分所有者が必ず加入することを法律で定められていて、かつ建物が存在する限り解散することはできない、ということです。
管理組合の「管理者」について
- 私の住むマンションでは賃貸する方が増えたり、また、高齢化により役員を辞退する人が増えてきています。そうした場合には、管理人をおいてはどうか、と知人から言われました。管理組合の「管理者」の役割を教えてください。
区分所有法第26条では、「管理者は、共用部分や当該建物の敷地及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」としています。
つまり、管理者は区分所有者全員を代表(代理)してマンションの管理を行うわけで、区分所有者の共有に属する共有部分、建物の敷地及び附属施設を保存する行為を単独で行うことができます。
また、年1回の集会(定期総会)を招集して組合事務を報告することが求められ、総会の決議や規約に基づいた行為などを実行する義務があり、その他議事録や管理規約を保管し、規約や総会の議決に基づいて訴訟等の原告または被告になることができます。
管理組合の「管理者」について
- マンション管理組合の「管理者」はどういう人が務めることができますか。
多くの管理組合では理事長が管理者になりますが、最近では、区分所有者以外の外部の人・法人を管理者として総会の議決により選任することも増えてきています。
これは、輪番制の役員制度を取っている管理組合では、区分所有者が高齢を理由に理事等に就任することを断るといったケースが増え、また賃貸化する住宅も増えていることから、いわゆる「役員のなり手不足」という状況が出現しています。そこで、外部の者、例えば専門家である管理会社やマンシヨン管理士を理事等に就任できるように規約を改正する管理組合もあります。
管理者についても同様に管理業務を外部に委託することで、より円滑な組合の運営を図ろうとする管理組合も増えてきています。
つまり、管理者には、規約に定めた要件に合致し、集会で選任の議決をすれば、法人でも、個人でも管理者の職に就くことができます。
管理費と修繕積立金について
- マンションの購入を考えています。マンション管理組合は、区分所有者から管理費と修繕積立金を徴収するという説明を販売業者から受けました。どういうものですか。
管理費は、マンションの通常の管理(共用部分の清掃、消毒、ごみ処理、共用設備の保守維持や運転等=標準管理規約第27条記載)を行うための費用に充当されます。
修繕積立金は、計画修繕や建物の建替えに伴う調査費用などに充当するために取り崩すことができます。建物の建替決議がなされた場合においては、これまでに積み立てられた修繕積立金を決議時点での区分所有者に対して清算(分配)することになります。なお、建て替えに際して、区分所有者全員の合意がある場合は、建替組合に修繕積立金全額を引き継ぐことができます。
管理費や修繕積立金の額については、標準管理規約第25条第2項で、各区分所有者の共用部分の共有割合に応じて算出するものとされていますが、管理組合規約で別に定めることもできます(例えぱ、専有面積に関係なく、集合ボストやオートロック用インターフォンといったものは専有面積の多寡にかかわらず 1 戸に1つの設置となっていますので、そうした面を勘案することもあります)。
なお、この場合において使用頻度(1階住戸がエレベーターを使わない、といったこと)は考慮されません
管理組合理事長を辞めさせたい
- 管理組合理事長が独断で物事をすすめてしまい管理組合運営に支障をきたしているので辞めさせたいのですが、どのようにしたらいいですか。
マンション管理組合において、理事長や役員が暴走してしまうと運営に大きな支障が生じます。理事長が管理組合を私物化してしまうようなことがみられる場合には解任を検討しなければなりません。
【方法1】理事会で議決する(解職)
理事会での議決によって、理事長を「解職」させることが可能です。議決に要する賛成数が定まっていない場合、基本的には出席者の議決権過半数での議決になります。解職された理事長は、通常の理事に戻ります。
これは2017年に最高裁判所で行われた、理事会による理事長解任の可否をめぐる裁判の判決によって、可能だと明確化された方法です。
判決の理由は、裁判の対象となった理事長が理事の互選により選任された人物であったため、反対に理事会での決議により理事長の職を解くこともできるというものでした。そのため、この方法で理事長を辞めさせる場合は「理事の互選により理事長を選任する」と管理規約で定められているマンションである必要があるでしょう。【方法2】組合員が招集する総会で議決する(解任)
総会で理事長の「解任」を議案とし、議決することで理事の職位そのものを解くことが可能となります。総会の開催は基本的に理事長が行うものですが、他の組合員でも、組合員総数における5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上の同意があれば理事長に開催の請求が可能です。理事長は、請求から2週間以内に招集通知を送る必要がありますが、何らかの事情で通知が発せられない場合は、請求者が総会の招集をすることができます。総会を招集する請求者は、通常なら理事長が行うはずの組合員名簿の確認、出席票・委任状・議決権行使書の徴収といった実務を、自ら担当しなければなりません。なぜなら総会では理事長解任の可否が議案となるため、理事長が実務を自ら行うことは考えにくいからです。【方法3】監事による臨時総会で決議をとる(解任)
監事は理事会や他の組合員の承認を得ることなく、総会の開催を理事長に請求できます。一般の組合員が招集する総会と同様に、理事長の「解任」を議案として決議することで、理事長を辞めさせられます。
ただし、請求は理事長の不正やその恐れがある行為を認めたときに限ります。
そのため、総会開催の根拠が不確かなまま招集してしまうと、開催議案や表現によっては中傷と捉えられ、理事長から提訴される恐れがあるので注意しましょう。【方法4】裁判所に解任を訴える(解任)
区分所有法の第25条に基づき、理事長が違法行為をしていたり、精神異常といった職務を行うに適さない事情があったりする場合、理事長の「解任」を裁判所に請求することができます。
マンションの管理会社の清掃業務等の業務の履行について
- マンションの管理会社の清掃業務等に不満があります。管理員がなかなか清掃しなかったり、共有部分の不具合、破損設備の故障を速やかに動いてくれません。
どのように是正させたらよいですか。 管理会社の業務内容は管理委託契約の内容によりマンションごとに異なります。従って管理会社と締結した管理委託契約をよく確認しましょう。
一般的に管理委託契約は民法643条に規定する委任契約の性質に当たるものと考えられ、委任の規定が適用されることになります。
管理会社は委託契約に従い善管注意義務をもって敷地や共有部分の管理をする必要があると考えられます。
管理会社に不適切な対応があれば管理組合を通じて改善の要求をしましょう。
高経年マンションについて
- 建築後50年のマンションの購入を検討しています。
知り合いからこのマンションは「高経年マンション」だといわれました。
「高経年マンション」とは何ですか。購入の際にどのような点に気を付けたらよいですか。 高経年マンションとは、明確な期間の定めはありませんが、建設後相当の期間が経過したマンションをさします。このようなマンションは、「居住者の高齢化」や「建物の老朽化」といわれる2つの老いが特に問題とされています。
このようなマンションを購入する場合には、管理組合の管理体制をよく確認し、管理が適正に実施されているかや長期修繕計画がきちんと定められており、修繕積立金の状況が適正であるかなどもしっかり確認するようにしましょう。
このことを踏まえて、重要事項説明書に記載された内容を十分に確認し疑問点等を解消してから契約手続きをしてください。
マンションの管理組合として、放置自動車を撤去する方法を教えてください。
- マンションの管理組合の役員をしています。連絡がつかなくなった区分所有者の契約している駐車場区画に自動車が、1年以上放置されており、困っています。勝手に処分すると個人の責任となってしまうようなことも聞きました。撤去するための手続きを教えてください。
マンションの管理組合として、放置自動車を撤去するための手順については、まず、放置自動車の状況を詳細に調査し、写真を撮るなどして記録を残します。車両の位置、状態、ナンバープレートの情報などを詳細に記録します。警察に相談することも考えられます。
また、車両のナンバープレートから陸運事務局などで所有者(使用者)の情報を確認し,所有者等が判明した場合、その所有者等に対して車両を撤去するよう書面で通知します。通知書には、撤去を求める理由と期限を明記し、証拠として残るようにします。
所有者等が判明しない場合や連絡が取れない場合、マンションの共用部分や掲示板に公告を掲示します。公告には、一定期間内に車両を撤去しない場合、管理組合が撤去手続きを行う旨を明記します。
所有者等が対応しない場合や所有者等が判明しない場合、管理組合は土地所有権に基づく妨害排除請求訴訟を裁判所に提起し、勝訴判決を得て、強制執行することとなります。弁護士に相談し、適切な法的手続きを進めることが重要です。
法的手続きが完了した後、専門業者に依頼して放置自動車を撤去します。撤去費用は、所有者等に請求するか、管理組合が負担することになります。
放置自動車の撤去を決定した場合は、マンションの全住民に通知し、透明性を保つことが重要です。
放置自動車が再発しないように、マンションの規約を見直し、駐車場の利用規定を厳格にするなどの対策を講じます。
ゴミ出しルールの徹底について
- 居住者の多様化に伴い、ゴミ出しルールの違反が増えています。張り紙等の対策はしていますが、効果がありません。 管理会社からも管理組合として対応を求められておりどのように対応したらよいでしょうか。
市区町村が作成したごみの分別のガイドブックとマンションのゴミ出しルールを明記したリーフレット等作成し全居住者に配布したらいかがでしょうか。また、多言語対応のガイドブックを用意し、外国人居住者にも理解してもらえるようにします。
居住者の意見を聞きゴミ捨て場の環境を改善することも大切です。分別用のゴミ箱や案内板を増設し、ゴミ捨て場を清潔に保つことで、居住者がルールを守りやすくなります。
管理会社と定期的にミーティングを行い、ゴミ出し問題の現状や対応策について情報を共有し、連携を強化します。
なかなか改善されない場合には、居住者のプライバシーに配慮しながら抑止力として防犯カメラを設置することを検討してもよいでしょう。
民泊禁止について
- 最近外国人の観光客が民泊を利用すると聞きました。不特定多数の人が出入りすると治安などが心配なので、私の所有しているマンションは、民泊を認めたくありません。どのような対策をしたらよいですか。
2018年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、住宅を使った宿泊サービス(民泊)を規制していますが、マンションの管理組合として、民泊を禁止するためには、規約改正が必要です。
規約を改正する場合は、管理組合の総会で民泊禁止に関する具体的な規約条項を提案し、特別決議(全住戸の4分の3以上の同意)が必要です
規約改正後、全ての入居者に対して新しい規約や罰則等を周知します。周知には、掲示板、回覧板、メールなどを利用し、全員に伝わるようにします。
規約改正後も管理組合や管理会社と協力して、民泊の兆候を監視します。入居者にも協力を呼びかけ、不審な動きがあった場合には報告してもらう体制を整えるとよいでしょう。
地方自治体の条例や規制を確認し、それに基づいて対策を講じ、必要に応じて、行政に通報し、協力を仰ぐことも大切です。
マンション大規模修繕工事中の防犯対策について
- マンション大規模修繕工事を行いますが、10階建てのマンションに足場が組まれるため防犯に対して心配の声があがっています。防犯対策について教えてください。
マンションの大規模修繕工事で足場が組まれる際に施工業者が、何らかの防犯対策を提案すると思われます。
ここでは、具体的な防犯対策をいくつかご紹介します。
管理組合としては、入居者に対して防犯意識を高めるための啓発活動を行います。足場が設置される期間中は、特に窓やベランダの施錠や二重の施錠の徹底について入居者に呼びかけます。不審者を見かけたらすぐに通報するなどのアドバイスを提供します。掲示板やメール、チラシを活用して情報を共有します。
現場には、動体検知センサー付きの照明が有効です。防犯カメラを設置をした場合には防犯カメラが設置されているとの看板も設置すれば、抑止効果を高まります。
警備員の配置、足場の出入口に鍵付きゲートを設置する等検討します。
足場にアクセスする工事関係者の出入りを記録し、身元確認を行うことを工事施工の条件にし、専用のビブスの着用といった身分証明の提示を義務付けるなど、厳格な管理を行うことを契約に盛り込むと良いでしょう。
しかしながら、警備員の巡回や防犯カメラの設置には、それ相応のコストがかかるため、見積もり提案時にチェックが必要です。
どこまで防犯対策を取り入れるべきかは管理組合の修繕積立金を使う工事ですから、最終的に多くの人に納得してもらえる選択をしたいものです。
マンション管理における地震発生時に起こるリスクについて
- 地震等によるマンション被害として、想定されるものはどのようなものがありますか。
さまざまな被害が想定されますが、一般的に次のようなことが想定されます。
○エレベーターが使えなくなる、緊急停止、閉じこめの発生。
○排水管が損傷を受けると、トイレが使えなくなる。
○照明、機械式駐車場、入口のオートロックなど共用設備が使えなくなる。
○受変電施設の機能停止。
○躯体・外壁の損傷やガラスなど落下物の発生
などです。
マンションは、規模や築年数などの違いにより個別のリスクが存在します。
住民参加型の防災訓練を企画するなど入居者同士のコミュニケーションをはかり、想定されるリスクについて話し合う機会を設けることも必要です。
【管理組合費等の滞納対策】 分譲マンション管理組合の理事長をしています。管理組合費等の滞納対策について、伺います。①
- Q-① 時効及び支払いの催告など
区分所有者が居住していたのですが、5年前に引っ越しをし、当該住戸は空き家になっていて、今は誰も住んでいません。管理組合費や修繕積立金は当該区分所有者名義の口座からが引き落とされていましたが、2年前から振り込みがなくなり、以来滞納が続いています。管理会社からは、その都度、転居先に電話や郵便による督促をしていますが、「銀行からの借金があり、管理組合費等についての支払いは困難だ」。という返答です。
今後、管理組合として、どういう対応をしていけばいいですか。 A―① 管理組合費や修繕積立金は、これまで裁判例により民法169条に規定される定期給付債権に当たるとされていたことから、2020年の3月末日までは消滅時効を5年間とされていましたが、2020年4月1日施行の改正民法では債権一般の消滅時効として166条で次のように定められました。
改正民法第166条
1 債権は、各弁済期から十年間行使しないときは、消滅する。請求できることを知った時から五年間行使しないときも、同様とする。
つまり、管理組合費等の納入期限から5年ないし10年を経過すると、時効が完成するので、その滞納金を請求できなくなってしまいます。
一般的に、改正民法150条の規定による催告(管理組合が区分所有者に対して、滞納している管理組合費等の支払いを求める書面を送付すること。)をすると、その時点で時効の完成が猶予(催告書面が到達した場合に6か月間は時効の完成が猶予されます。しかし、この催告を繰り返しても時効の完成を引き延ばすことはできません。)されます。
時効が完成する1か月前に催告すれば、6か月は時効の完成を引き延ばすことはできますが、その7か月間のうちに法的手続きを行う必要があります。
あるいは、区分所有者が管理組合費等の支払いを協議することの合意(書面によること)も時効完成の猶予となりますし、また、管理組合費の支払いを改正民法168条2項による承認書の交付があったときも時効が更新(承認した時点が時効期間の起算点となります。)されます。
改正民法第168条
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
本件の場合は時効完成までに相当の期間があるので、まず、配達記録付き内容証明郵便で区分所有者に滞納している管理組合費等の支払い及び支払いがない場合には法的措置を講ずる旨の催告を行い、その後は、支払督促や少額訴訟、差押などの裁判上の請求といった法的手続きの実施に向けて、弁護士に相談されることを勧めます。
なお、管理組合規約に遅延損害金の規定があれば、その規定に定める率を乗じて得た額を、規定がなければ、民法404条3項の規定(3%、法令により3年ごとに見直されます。)に従い請求することができます。
さらに、遅延損害金と併せて、「違約金としての弁護士費用等並びに督促及び徴収に要する諸費用も加算して請求できる(標準管理規約60条2項)」ことも規定しておくことも考えられます。
また、理事長がこうした訴訟提起などを行うことができる、とする管理組合規約に予め規定しておくとよいでしょう。
【管理組合費等の滞納対策】 分譲マンション管理組合の理事長をしています。管理組合費等の滞納対策について、伺います。②
- Q-② 区分所有者死亡とその相続人が所在不明である場合
区分所有者が1人で居住していたのですが、2年前に死亡しました。
管理組合費や修繕積立金は当該区分所有者名義人の口座からが引き落とされていましたが、死亡した翌月分の管理組合費から振り込みがなくなり、以来滞納が続いています。相続人である区分所有者の長男に滞納の事実と督促の連絡をしていたのですが、やがて長男あての郵便物は転居先不明で返送されるようになりました。
現時点での滞納月数は21か月です。なお、当該住戸の登記簿における区分所有者は、死亡した者の名義であり、相続登記はされていません。
今後、管理組合として、どういう対応をしていけばいいですか。 A-② まず、長男以外にも相続人がいるかどうか、の調査が必要です。
被相続人である区分所有者の住民票や戸籍謄本(改製原戸籍)で、調べることができます。
長男以外の相続人がいれば、相続財産は、相続人全員の共有が原則ですから、その者にも案分した割合で滞納家賃等を請求することになります。
しかし、相続人の所在が不明な場合は、住民票を管轄していた市町村への照会(転居を繰り返していた場合には、その都度)や調査事務所へ依頼して調査を行っていくことになります。
こうした相続人が行方不明であることを証する書類を作成の上で、区分所有法7条の先取特権による当該住戸の差し押え、競売、配当金交付要求といった手続きをとることで、未払いとなっている管理組合費等を回収していくことになります。
手続などについては、相当な法律知識と細かな実務経験が必要なので、早めに弁護士に依頼することを勧めます。
なお、住宅ローンなどで抵当権が設定されている場合がありますが、そうした場合の多くは抵当権設定登記の日の方が早いので、その場合は、先取特権としての管理組合費等よりも抵当権の方が優先されるでしょう。さらに、多くの場合は、抵当権設定と併せて団体信用生命保険に加入している場合もあるので、こちらの確認をすることも大切です。
※ 先取特権とは、「法律で定められた債権を有する者が、他の債権者に優先して弁済を受ける権利」です。先取特権は、抵当権や質権などと同様に優先的弁済を受ける権利ですが、先取特権は「民法」で規定されている権利であって、抵当権や質権は契約等を交わすことで成立する権利です。
【区分所有法7条】
一 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
二 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先取特権に準用する。※ 管理組合費等の滞納が区分所有者死亡以前のものの場合は、相続人が複数いて遺産分割協議が整っていないときは、法定相続相当分で分割して各相続人に請求することになります。
管理組合費等の滞納が区分所有者死亡以後のものの場合は、相続人が複数いて遺産分割協議が整っていないときは、全ての相続人に対して全額を請求できます。
【管理組合費等の滞納対策】 分譲マンション管理組合の理事長をしています。管理組合費等の滞納対策について、伺います。③
- Q-③ 相続人が相続放棄の陳述書を家庭裁判所に提出した場合
ある住戸の区分所有者が死亡したのですが、緊急時の連絡先として管理組合に届出のあった区分所有者の子供に確認したところ、その全ての相続人が相続放棄の手続をした、との返事でした。
なお、区分所有者が死亡した翌月までの管理組合費や修繕積立金については、区分所有者名義人の口座から引き落とされていました。
今後、管理組合として、どういう対応をしていけばいいですか。 A-③
まず、相続人を特定する必要があります。
本件の場合には、相続人である区分所有者の子供から、「相続放棄の申述をし、相続を放棄した」ということですので、死亡した区分所有者(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、すべての相続人が相続放棄の申述書を提出していることを照会するか、相続人らに相続放棄の証明書の交付を求めることになります。
その結果、相続人がいないことが判明した場合は、相続財産管理人又は相続財産清算人が選任されていれば、同人に対して、未払いとなっている管理組合費等を請求していくことになります。
もし、相続財産管理人又は相続財産清算人が選任されていなければ、上記家庭裁判所に選任の申し立てる(相当額の予納金の納付を求められる)ことが考えられます。この場合、選任された者に対し、先取特権として管理組合費等の支払いを求めていくことになります。
いずれにせよ、相続放棄の陳述の照会や申立などの手続を含め、弁護士への委任を考えた方がよいと思われます。
置き配について
- マンションの共用部分の置き配について、住民から正式にルール化してほしいとの要望があります。どのように考えたらいいですか。
本来、共用廊下は共用部分であり、マンション内の通路で、他の住民も利用しているため、組合員がそれぞれ勝手な使い方をすることはできません。
消防法に基づき、廊下、階段、避難口等に避難上の支障となるような状態での宅配物等の放置を禁止していることについては留意しなければなりません。
しかしながら、2024年6月7日に国土交通省が、新しいライフスタイルの変化に対応するために「置き配に関する使用細則を定める際のポイント」を公表しています。管理組合として置き配を認める場合の参考にしてください。
EV(電気自動車)用充電設備の設置について
- EV(電気自動車)用充電設備の設置を検討しています。設置のすすめ方についについて教えてください。
2024年6月7日に「マンション標準管理規約」が改正され、EV充電設備を設置する際には、マンション管理組合は、普通決議で決定することが可能となっています。
設備の設置場所や使用方法、費用負担について具体的なルールを策定します。充電設備の使用上のルールや使用料についても、併せて駐車場使用細則等に定めます。
決議が通った後、電気工事業者に依頼して設置工事を行い、マンションの他の設備や生活に影響が出ないよう配慮します。
マンション管理員の休暇について
- 管理会社との契約更新にあたり管理員が休暇を取ることについて明確化したいという要望がありました。従わなくてはいけないのでしょうか。
令和5年9月に国土交通省が、働き方改革に関する対応として「マンション標準管理委託契約書」を改訂し「別表第2管理員業務」の「1(2)勤務日・勤務時間」及び「1(3)休日」に計画的休暇が追加され、「41 別表第2関係」に休暇等の記載が追加されました。社会情勢から管理員・清掃員の確保が困難になってきている状況を鑑みての改正となっています。
管理会社から働き方による要望があった場合は、管理会社と管理業務の効率化等について、「マンション標準管理委託契約書」の改訂内容にのっとって管理会社と話し合いをおこない、管理内容を変更するにあたっては、組合員に理解を求めたうえで決定することも大切です。
マンション管理適正化診断サービスについて
- マンション管理適正化診断サービスについて
マンション管理適正化診断サービスは、一般社団法人日本マンション管理士会連合会(日管連)による制度です。マンション管理組合の申込みに対し、日管連所定の研修を受けたマンション管理士が管理状況の診断を行い、レポートの提出を受けられます。
この制度のメリットは、無料で国家資格者のマンション管理士の診断を受けられることです。
もう一つとしてのメリットは、診断結果に応じて、日管連と提携保険会社のマンション損害保険の割引を受けられる場合があることです。
保険料の負担が課題となっている管理組合、専門家による管理状況の評価を受けてみたいとお考えの管理組合は、検討してみてください。
マンション管理計画認定制度とマンション管理適正評価制度の特徴や認定を受けるメリットはなんですか。
- マンション管理計画認定制度とマンション管理適正評価制度の特徴や認定を受けるメリットはなんですか。
マンション管理計画認定制度とマンション管理適正評価制度の違い、認定を受けるメリットについてそれぞれの違いや特徴、認定を受けるべきかどうかについて説明します。
1. マンション管理計画認定制度
令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正(令和4年4月全面施行)され、「マンション管理計画認定制度」が創設されました。
「マンションの管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとしてマンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体(市の区域にあっては当該市、町村部の区域内にあっては都道府県)の認定を受けることができる制度です。認定を取得することで、以下の効果が期待されます。区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる
(出典 国土交通省「マンション管理・再生は新時代へ」)2. マンション管理適正評価制度
一般社団法人 マンション管理業協会が実施する制度で、第三者の専門家がマンションの管理状況を評価する仕組みです。星の数(1~5段階)で管理状況が評価され、外部からの客観的な評価が得られます。
認定を受けるメリットとしては、管理状況が見える化されるため、資産価値の透明性が高まり、第三者の評価によって、購入希望者や金融機関から信頼を得やすい。評価結果をもとに改善点を把握し、適切な対策が取れる。などがあげられます。3. 両方の認定を受けた方がよいか?
マンション管理計画認定制度は自治体からの認定を得ることで公式な評価が得られ、資産価値の維持に役立ちます。
マンション管理適正評価制度は、客観的な第三者評価により、透明性や改善点が把握でき、運営の効率化に寄与します。
両方の認定を受けることで、資産価値の維持と住民の安心感が大きく向上するため、可能であれば両方受けること検討されたらいかがでしょうか。
カスタマーハラスメントについて
- マンションの管理会社から、ある特定の組合員が、管理会社に対して様々な要望を高圧的に伝えてきて困っていると管理組合役員に報告がありました。 どのようにしてカスタマーハラスメントのないマンション管理組合にしていけば良いでしょうか。
令和5年9月に国土交通省が、「マンション標準管理委託契約書」を改訂し「カスタマーハラスメント」についての内容が追加されました。以下の条文を理解し、管理委託契約を改訂するため、管理組合と管理会社で協議、検討し総会決議の上、管理規約の改訂を諮る必要があると思われます。
[第8条関係]
<管理業務の指示>
管理組合が管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、管理組合が指定した者以外から行わないことを定めた条文です。
このことにより、指定された組合員からの相談や要望を受付けることとして、カスタマーハラスメントを未然に防止することが可能です。
[第12条関係]
<有害行為の中止要求>
組合員等による管理業者の使用人等に対する具体的な例が記されています。
①本契約に定めのない行為や法令、管理規約、使用細則又は総会決議等(以下「法令等」という。)に違反する行為を強要すること
②侮辱や人格を否定する発言をすること
③文書の掲示や投稿、インターネットへの投稿等による誹謗中傷を行うこと
④執拗な付きまといや長時間の拘束を行うこと
⑤執拗な架電、文書等による連絡を行うこと
⑥緊急でないにもかかわらず休日や深夜に呼び出しを行うこと
等をあげています。
管理組合はカスタマーハラスメントに対して、特定の個人、管理会社の問題として傍観するのではなくカスタマーハラスメントに対する連絡体制や対応策等について、管理会社と協議の上、管理組合として組織的に対応することが必要です。
管理組合と管理会社はお互いを尊重し、より良い住環境の形成に向け日頃のコミュニケーションを大切にし、相互の信頼関係を築くことが大事です。
専有部・共用部について
- 分譲マンションの網戸が古くなっており、交換をする場合の費用は誰が負担するのですか。
網戸は標準管理規約で共用部分とされており、その部屋の特定の区分所有者のみが使用するものなので、共用部分のうちの専用使用部分です。
専用使用部分の「通常の使用に伴うもの」は専用使用権を有する者の負担となりますので区分所有者の負担になります。
ただ、共用部分の為、自己判断で交換できません。管理規約を確認のうえ、管理組合の許可を得てください。